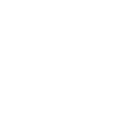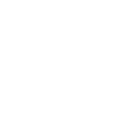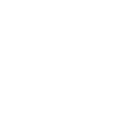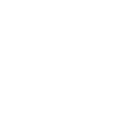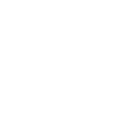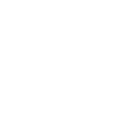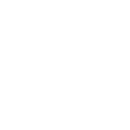トピックス
育児介護休業法の改正について
2025/03/04
育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法が改正されます。※以下は本記事作成時点(令和7年3月4日)のものです。
育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日以降、順次施行されます。
改正点は多くありますが、本記事では、重要な点に絞ってご紹介します。
① 子の監護休暇の拡充
現状、「小学校就学前の子」がいる従業員は、1年に5日(場合によっては10日)まで、「病気・けが」「予防接種・健康診断」のための休暇が取得できます。
今回の改正では、対象となる子が「小学校3年修了までの子」に拡充されました。
また、取得理由も、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園式や入学式、卒園式」が追加され、拡充されています。
なお、労使協定があれば、「入社6か月未満」の従業員は除外できるとされていましたが、改正後は除外できなくなりました(介護休暇についても同様になります。)。
② 残業免除請求者の拡充
現状、「3歳未満の子」がいる従業員が一定の条件を満たせば、時間外労働をさせないように企業に求めることができます。
今回の改正では、対象となる子が「小学校就学前の子」まで拡充されました。
③ 育児休業の取得状況を公表する対象企業の拡大
1年に1回、男性従業員の育児休暇取得率等を公表しなくてはならない企業が、現状では「従業員1000人超」の企業ですが、法改正後は「従業員300人超」の企業となります。
④ 介護離職防止のための雇用環境整備
次の4つの措置のうち1つ以上を講じなければならないとされています。
ア 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
イ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ 自社の従業員の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
エ 自社の授業員へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
現行法でも、育児休業申出の促進のために同様の措置を講じることが義務付けられており、これを応用される企業が多いのではないでしょうか。
⑤ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
介護に直面している従業員の対応と、介護に直面する前の早い段階での従業員の対応があります。
ア 介護に直面したと申し出た従業員への周知・意向確認
申出を受けた企業は、以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません(ここで取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認をしてしまうと、義務を果たしたといえない可能性があります。)
個別周知・意向確認の方法は、面談(オンライン可)、書面交付が原則です。従業員が希望すれば、FAX、電子メール等が可能です。
(周知事項)
・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
・介護休業・介護両立支援制度等の申出先
・介護休業給付金に関すること
イ 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
実際に介護に直面していなくとも、40歳前後の従業員に対して、上記アの周知事項について情報提供しなければなりません(方法も同じ)。
⑥ 柔軟な働き方を実現するための措置等
3歳~小学校入学までの子がいる従業員に関して、以下5つの中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。その際、従業員過半数代表等からの意見聴取を行います。
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日以上/月)
・保育施設の設置運営等
・就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
・短時間勤務制度
従業員は、企業が選択した措置の中から1つを選んで利用できます。
なお、3歳未満の子がいる従業員に対しては、一定期間の間に、企業が選択した措置の内容、対象措置の申出先、所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度を個別に周知し、制度利用の意向があるかを個別に確認しなくてはなりません(方法は⑤と同様)。
⑦ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
従業員が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、子が3歳になる前の一定期間において、以下の事項について、従業員の意向を個別に聴取し、配慮しなければなりません(以降確認の方法は⑤、⑥と同様)
・勤務時間帯(始業および終業の時刻)
・勤務地(就業の場所)
・両立支援制度等の利用期間
・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
以上が今回の法改正のポイントです。
①~⑤は令和7年4月1日から施行され、⑥~⑦は少し遅れて同年10月1日から施行されます。
(その他、3歳未満の子がいる従業員についてテレワーク導入するといった努力義務等が課されています。)
「育児と仕事の両立」「介護と仕事の両立(介護離職の防止)」は、社会全体のテーマになっていますので、今回の法改正の趣旨は十分に理解できるものです。
しかしながら、従業員を雇用している企業にとって、育児や介護の両立のためにすべきことが増え、しかも複雑化しています。
法改正に対応するために就業規則の見直しをしなくてはなりませんし、運用しなくてはなりませんから、企業の労力・時間の負担は相当なものだと推測します。
違反した場合は行政指導の対象となり、是正をしないと公表されかねない事柄ですし、優秀な人材を確保する観点からも、法改正を踏まえた対応が企業には求められています。
◇ 横浜で会社・企業側の労働問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。